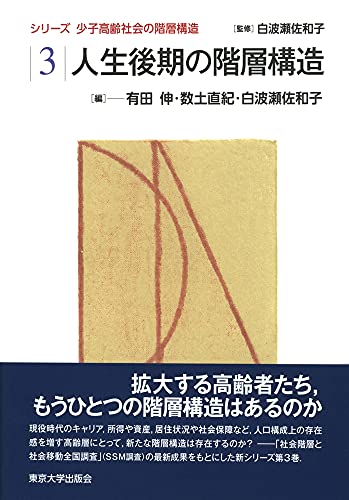11-4-2-4)積極的注意と受動的意識
目標を検出する努力感(積極的注意状態)が、帯状回前部の活動を伴うのとちょうど逆に、例えば、目覚めて頭がぼんやりしているような思考を空にして受動的意識状態にすることは、帯状回前部の活動停止を伴う。
つまり、帯状回前部が、「積極(能動)性と消極(受動)性」との入り切りスイッチの役目を担う。
ということは、意識を空にする、心の受動性を保つには、帯状回、特に帯状回前部(前部帯状回、前帯状皮質)の機能を停止させなければならない。これは、瞑想時に不可欠な機能である。意識を、心を漂わせる状態にする。
11-4-2-5)受動性と能動性
例えば、「聴く」と「聞こえる」について。耳からボトムアップする音声に注意を向けることなく聞き流すのが、聞こえる(受動的意識状態)、である。これは受動性意識段階である。
その聞こえて来る音声に、トップダウン注意を向けるのが聴く(積極的注意)、である。このことは、同じく「見る」と「見える」についても妥当する。
結論を言えば、帯状回前部が、報酬(メリット、デメリット、目的、目標、望ましい物など、今現在注目するにあたいする)情報に基づいて、行動への準備や切り替えをする役割を担っている。
つまり、ロックオン機能である。それは、ロックオンした情報以外を排除することでもある。つまり、注意機能である。別の表現をすれば、フィルター機能である。
11-4-2-6)注意と脳部位(特に帯状回)
あらためて、注意とは、トップダウンであろうとボトムアップであろうと、感覚器を通して入り込む膨大な情報から特定の有用な、あるいは重要な情報を選択し、その選択している状態を維持する働きである。言い方を変えると、選択した情報を優先処理し、選択されなかった情報の処理を抑制する機能である。
それに関わる脳部位に関して言えば、例えば、「前頭葉背外側部と帯状回前部」の間に密接な神経的連絡があり、「注意」を必要とする多くの行動において、両者が重要な役割を果たす。
別の例を挙がれば、被験者に視覚的あるいは聴覚的に単語を提示して、その意味を思い出すよう要求する。つまり、能動的に言語を伴う処理をする際には、帯状回前部(積極性)と、言語に関連する左脳の前頭葉と頭頂野、外側前頭後頭の意味野(言語理解)がともに活動する。
更に別の例を挙げると、意味のある単語を聞くと、両(右脳と左脳)側の側頭野内聴覚連合野と、注意力に関係する左帯状回前部が活動する。
11-4-2-7)帯状回の機能
大脳辺縁系の一部である帯状回は、動機付けの中枢とされており、やる気を起こすかどうかはここで決まる。帯状回の中でも、特に帯状回前部(前部帯状回)は、「能動的な注意や意志や意欲」を生み出す場である。
注意状態が必要な作業記憶課題では、帯状回前部と前補足運動野が重要な役割を果たす。
注意を向けた意味のある感覚刺激に対して、それを受ける感覚野の特定部分での神経活動が増大する。その際には、その情報だけを選択的に感覚野へ伝え、それ以外の部位からの神経活動(情報)は遮るという効率的選択の機能に帯状回は関わる。これは注意機能そのものである。
第三章:情報(知)の発達と階層性 11)精神、性格、意志、注意、理性 注意と意識(能動性、受動性)
注意と意識(能動性、受動性)
11-4-1)脳の働きと注意
脳は、断片的、要素的な情報から、部分的な統合を繰り返しながら、複雑な総合的、統合的な全体像を形成してゆく。あたかもジグソーパズルを完成させるかのように。
注意は、そのように全体像を形成して行く途上で、不必要な情報を排除し、必要な情報だけを選択する(能動的な)機能である。
11-4-2-1)二種類の注意
その注意機能には二種類ある。
(1)(外因性、瞬間的、受動的)ボトムアップ注意
ボトムアップ注意は、無意識的に行われる、自動的で瞬間的に生じる、強い刺激によって誘発される、定位反射(刺激対象に顔や体を向ける無意識的反射行動)である。危険性の高い事柄に際して、強力に突発的に割り込んで来る。あるいは、外にある、または内から上がって来る強い刺激や欲求に押されて、思わず向かう注意である。
(2)(内因性、継続的、焦点的、能動的)トップダウン注意
ボトムアップ注意が無意識的であるのに対して、トップダウン注意は、意思に基づいて、意識的に、従って随意で引き起こされ、精神的な努力を求められる注意機能である。
11-4-2-2)注意とその際に働く脳部位
外因性瞬間的無意識的ボトムアップ注意は、後頭頂葉と視床枕とで発せられる機能である。
注)視床枕は、大脳新皮質の視覚野と密接に連携している。注意を向けると、視床枕で、注意対象に関する視覚情報が処理され、それ以外の物に関する視覚情報が除外される。
他方、内因性継続的焦点的トップダウン注意は、前頭前野(帯状回前部)が指示を出す。トップダウン注意は意識的なので、精神的な努力を必要とする。
例えば、本に向けていた注意が、近くでの突然の大きな音によってその注意が奪われるとすれば、本への意識的トップダウン注意が、大きな音への無意識的ボトムアップ注意へと瞬間的自動的に切り換わったと言える。
注)脳内では、常に情報による勝ち負け(生存)競争が繰り広げられている。勝利した情報が行動化を勝ち取る。この場合には、上位か下位かは関係なく、勝った情報が実行を勝ち取る。
11-4-2-3)注意と帯状回前部
例えば、本の中の文字を受動的に見る(受動的意識段階)際には、帯状回前部は活動しない。ところが、新しい単語を考え出したり、特定の目標を注目するときには活動する。つまり、前頭葉の中心線に沿った帯状回前部は、トップダウン型能動的選択的注意システム(の中心)として働く。能動性注意には帯状回が働く。
逆に、出現頻度の低い目標を検出するために、単語のリストに注意するとき、主観的な感覚としては、「頭の中の思考や感覚を空」にしている、つまり、ぼんやりと視線を定めずに入って来る情報を眺める感じである。流れて来る情報の内で、引っ掛かる物が来たら、それに注意を向ける。この主観的な意識を空にする(受動的意識段階)では、帯状回前部の活動の低下が同時進行する。
第三章:情報(知)の発達と階層性 11)精神、性格、意志、注意、理性 自意識(自己意識、自我意識)から内省へ 11-3-1)自意識、自己意識、自我意識
自意識(自己意識、自我意識)から内省へ
11-3-1)自意識、自己意識、自我意識
時々に刹那刹那に上がって来る欲求に従って動くのでは、とても浅い動きでしかない。深い、意味深い行動を選び取るには、自身の中に存在する知的資源を知らねばならない。それには、自身の心の中に潜って探索をする必要がある。その方法の第一段階が、自己意識である。
自己意識や自他の区別には、右半球(右脳)が主要な役割を担う。前頭前野(その内でも最先端)が、上位階層レベルの認知過程と深く関わっている。
もう一人の自分がいて、自分のことを上から客観的に見て、自分自身を制御する。これを「メタ認知」という。行動する主観的自分を、一段上の階層から観察(モニター)する客観的自分(自意識、自己意識、自我意識)を持つことで、自己に関するメタ認知が働く。
生後1歳半から2歳頃になると、当惑する、嫉妬するなどの自己を意識した行動(感情)が表れる。つまり、他人の目を意識する。他人に自分がどう映っているのかが気になる。幼児は2歳前後に自己意識(客観的自分)を獲得し始める。これは、ゾウやイルカや、チンパンジーやオランウータンなどの大型類人猿は持つが、ニホンサルは持っていない。
この自意識とは、初期には、他人から見られている、注目されていると感じる(意識が働く)ことである。だから、動作がぎこちなくなる。外界に向けられる意識だけではなく、外(対象)に向かった意識が鏡に当たって跳ね返り、その鏡上の自分自身にも同時に向けられる上下二層の意識である。
注)思春期になると、多かれ少なかれ自意識過剰気味(自分は他人からどう見られているのだろう、自分の行動は他人からどう感じられているのだろうか)になる。これが自分を振り返る大きな動機と成り得る。
11-3-2)反省から内省へ
自意識(他人から自分はどう見えているのか)から発展して、自己の感覚や感情や動機など、自分が現在体験している事柄に注意を向けることができる「反省」「内省」(自分の心を知ろうとする働き)がある。この外に向かっていた自意識から、更に発展して自分の内面に向かう内省は、外に意識が向かう自意識(他人には自分がどのように見えているのだろうか)よりも高次な機能(他人からどう見えているかよりもより客観的に心の中を探索する機能)である。自分に対する他人の態度から自分自身を判断することから、自分の内面(心の中)を直に探索する行為が反省、内省である。
しかし、それが可能になるには、脳幹網様体(内省のために外界情報を遮断する機能を持つ)の完成を待たなければならない。更には、前頭前野と連携しなければなしえない。脳部位で言えば、前頭葉内眼窩前頭皮質が、実際の行動と予測行動とを比較検討する。また、他者目線で自己評価をする場合には、背側部が関わる。どちらにしても、内省は前頭前野の機能である。
5、6歳頃から、周囲の状況と自己の能力を考慮して起こりうる事態を予測するなど、いくつかのメタ認知的機能について成人と同様の能力を持ち始める。
第三章:情報(知)の発達と階層性 11)精神、性格、意志、注意、理性 知性から精神へ 11-1)知行合一
知性から精神へ
11-1)知行合一
私は、上で述べたように、精神機能の一つであるべき知性を、精神から切り離した。というのは、知性は図書館(知の集合体)である。知性は行動する競技場にはなり得ない。
王陽明(中国明代の儒学者、哲学者、高級官僚、武将)は言う。「知行合一」と。「知は行の始なり、行は知の成るなり」(知ることは行為の始めであり、行為は知ることの完成である)。行動を伴わない知識は未完成(熟れていない果実)である。ということで、ここからは知性を精神化(行動化)する脳部位、脳システムを述べて行きたい。
精神と前頭葉
11-2)精神を、「能動的」で「知性的」な働きであると、ここでは限定的に捉える。精神は、知性的存在者の認識能力、判断能力、意志能力、の総称である。ということで、ここからは特に「意志能力」に関して述べて行く。
その精神が、行動面に現れるのが性格(自発的、主体的、意欲的、積極的、心優しいなどなど)であり、これも大脳新皮質(特に前頭前野)の働きである。大脳新皮質の内でも前頭前野は、創造(未来)性に大変関係が深く、物事を組織立てる働きをしている。それ以外にも、予測、推論、善悪の判断、衝動的な感情の暴走を抑制するなどの働きをする。
注)脳>大脳>大脳皮質>大脳新皮質>前頭葉>前頭連合野(前頭前野)。
第三章:情報(知)の発達と階層性 11)精神、性格、意志、注意、理性 知の階段
11)精神、性格、意志、注意、理性
知の階段
11-0)この本全体のテーマ(主題)の一つが、階層構造である。そして第三章のテーマが、情報(知)の発達と階層性である。人間においては、脳内の情報(知)の発達と、心の成長発達とは、並行しているというか、脳内の情報(知)の発達=心の成長発達、ともいえる。ということで、ここで心の成長発達についてまとめてみたい。
まず赤ん坊が生まれて、始めにしなければならないのは、ほとんど空っぽの脳(大脳新皮質)に、経験を通じて、感覚器官を通して、感覚情報をどんどんと流入させることである。
つまり、知の第一階層は、感覚情報で構成される。この知の第一階層は、脳部位としては、脳幹の視床が最高決定中枢である。この階層での発信方式は、反射である。第一階層は感覚情報を受信して大脳新皮質に送り届けることが大きな機能である。この段階では、大脳新皮質は単なる感覚情報の初歩的処理工場に過ぎない。
次の第二階層は、感覚情報を元にした発信が大きな機能である、つまり、感情の階層である。実に様々な感覚情報が身体内外から感覚階層(第一階層)に、刻々と流入して来る。それを元に、個人として統一した行動を取らねばならない。それを行うのが、第二階層である、自我を拠点とした感情階層である。この階層を取り仕切る脳部位は、大脳辺縁系の扁桃体である。この段階に成って第二階層である扁桃体が最高決定中枢として機能する。
だが、扁桃体は、競争原理に立つ個人にとっての最適な判断を下すが、社会生活を営む年齢にあっては、個人優先だけでは、争いが絶えない。
だから、次に第三階層として、知性階層が積み上げられた。この第三階層は、大脳新皮質の後部(後頭葉、側頭葉、頭頂葉)が責任部位である。そこでは、視床などから送られた感覚情報が、高度に処理されて知性に生まれ変わる。第一階層が主に生の感覚情報を扱うのに対して、第三階層は、それを高度処理して知性化する。大脳新皮質後部脳部位は、個別的能力を担う。例えば、言語理解とか、計算能力とか、絵画作成とか、作曲とか。これは、前頭前野が障害されていても可能である。この段階では、知性的には、つまり個人の能力は素晴らしくとも、社会人としては疑問符が付く。
最後の第四階層を、このセクション「11)精神、性格、意志、注意、理性」で取り扱う。私は、第四階層を精神(理性)と名付けたい。第二階層が、感覚情報を元に、自我を拠点として判断し、行動化する機能であった。様々な感覚を一つにまとめ上げるのが、あるいは優先順位から選び取った結果が、感情であった。だがしかし、感情は自分の立場からの判断であった。命の取り合いをする動物段階では当然の判断機能だろう。
だが、それを超越したはずの人間界にあって、社会性を高めるためには、また知性が有力な生活手段になった今では、自分本位の感情のまとわり付いた知性は、感情から解放しなければならない。感情から解放された知性は、冷静である。だがしかし、今度は、感情が持っていた無意識的行動化エネルギーを、知性はなくしてしまう、という代償を支払った。再度エネルギーを注入したければならない。
注)怒りという情動から行動に移すには、内的エネルギー源である視床下部が必要である。というのは、視床下部は、身体というエンジンを吹かす働きがある。また、知性を生み出す大脳新皮質は、怒り反応へは関与せず、逆に視床下部を抑制して怒りを鎮めさせる立場にある。
この第四階層は、出来るだけ幅広い分野からの情報を集めて、それらを統合して、一つの結論を下して、行動化する機能だと定義したい。精神、理性は、個人性をはるかに超え出ている。しかも、精神も理性も、統合してまとめる働きを持つ。
なお、ユングは、第四階層に直観を掲げた。だが、私は直観ではなく精神とした。直観は、ボトムアップ式(無意識的)に上がって来る判断機能である。だが、精神は、判断機能であると同時に実行機能をも併せ持つ。だが、その行動化には、下位階層の協力が必要不可欠である。
この第四階層は、前頭前野が主導している。前頭前野は、感覚情報を受け取り、感情を受け取り、知性を受け取り、内面から上がって来る欲求を、外界状況を考慮しつつ、優先順位を定めながら、選択して、企画する機能を持つ。
第三章:情報(知)の発達と階層性 10)知性、言語、思考、意識 10-6)知性とは
10-6)知性とは
ある男性が、脳腫瘍で左右の前頭前野が手術によって切除された。知能が高かったその男性は、手術後も、知性レベルにほとんど変化はなく、記憶も損なわれず、言語活動や運動能力にも変わりがなかった。要するに、IQは、前頭前野切除後も低下していない。
この10)セクションのテーマ(主題)として、知性、言語、思考、意識という単語を掲げた。それらを繋いで文を作ると、知性とは、意識上で、言語を用いて思考する作業と言える。
では、知性とは言語を用いなければならないのか。言語を用いないなら知性ではないのか。それは違う。言語を用いるのは知性の一つに過ぎない。ならば知性とは何なのだろうか。
「知性」とは、「大脳新皮質で高度に処理された感覚情報を駆使して表現する能力や行為」だと言える。例えば、音楽、絵画、彫刻、造園、歌、手芸、ダンス、将棋、文学、などなど、多種多様な文化的表現手段が揚げられる。
音楽では、聴覚から入った音声が、単音や複合音、具体的には、和音、更には協和音、不協和音、更にその上に、旋律、さらにはリズムの加わって全体的響きとしての音楽が形成される。人の脳には、これを生み出す能力も、これを鑑賞する能力も持ち得ている。これは、音を多層的に高い階層構造に組み上げる能力を意味する。
大脳新皮質には、上で揚げた例以外にも、多種多様な知性的表現手段を可能にする潜在的可能性が眠っている。これから先も、新しい知性的表現が発明され、人々の心を豊かにして行くだろうと確信している。
ただ言えることは、言語的知性的表現ではなくとも、他人への意思伝達には、言語が大きな役目を担い続けるだろうとは思える。つまり基盤には言語が必要とされると。
第三章:情報(知)の発達と階層性 10)知性、言語、思考、意識 思考(言語の進化:コミュニケーション言語⇒独り言⇒思考) 10-4-1)意思疎通言語⇒独り言⇒思考
思考(言語の進化:コミュニケーション言語⇒独り言⇒思考)
10-4-1)意思疎通言語⇒独り言⇒思考
言語は、外界(社会)に向けては、コミュニケーションの手段である、と述べた。内界(心の中)に向けては、思考の手段である。考えるとは、内的作業である。とは言え、図式を描いたりして、外化させることも多いが。
幼児は、思考の前段階として独り言を言いながら、つまり、自らがしゃべり自らが聞きながら、思考する。つまり、側頭葉(聞く機能)と前頭葉(話す機能)とが、まだ統合されていない段階である。これは、他人との会話と、純粋な内的思考との中間期(中間形態)であろう。
自らとの無言の対話をするためには、外界からの、また身体内部からの感覚的な情報をできるだけ阻止しなければならない。でなければ、ボトムアップ感覚情報とトップダウン思考言語とが、脳内で入り混じり収拾が着かなくなる。
更には、思考は、考える中身、テーマを定めて、必要な情報を脳内から呼び出して、秩序付けて並べる必要がある。そのような思考に中心的に関わる脳部位は、前頭前野である。
10-4-2)シミュレーションとは
シミュレーションとは、想定される条件を取り入れて、実際に近い状況をつくり出す模擬実験である。見えない行動の結果を見える化することである。思考とは、それを脳内で実施する、脳内シミュレーションである。
思考は意識というまな板の上での作業
10-5-1)意識は社長職
生の感覚情報は、例えば、視覚や聴覚などは、大脳新皮質各種感覚野で処理されて、更には情動(扁桃体)や思考(前頭葉)への素材として変換すべく大量の作業を施される。
意識は、それらの作業段階の内で、志向性を持つ高次情報処理段階である。意識は、比喩的に言えば、最終的報告書を読む社長職である。様々な情報が、意識に上がって来る時には、高度に加工処理が施されている。比喩的に言えば、店から買った食材が料理として出されている段階である。生の食材は見せてもらえない。
10-5-2)意識と注意と脳部位
意識と注意は、7)「心の成長発達」のセクションで言及したが、感覚情報が脳の情報処理の中で、下位階層から順次自動的に情報処理されて上がって来る過程に対して、能動的に情報を求めて選択し統合して、目的の行動との間に整合性をもたらすべく実行するトップダウン的情報処理方式である。
この過程を脳的に言えば、感覚情報は、視床を介して大脳新皮質に送り出すことで自ずと大脳新皮質を活性化させ、目覚め状態を作り出す。この段階は、大脳新皮質にとって、ただ門戸を開いて情報を入るに任せているボトムアップ型受動的意識状態である。ボトムアップ型意識の中枢は、視床(と脳幹網様体)である。網様体は、大脳皮質の神経細胞(ニューロン)に信号を送って、刺激を与えることで意識状態を生み出す。その網様体自身も、様々な感覚からの情報によって活性化される。
その意識状態にあって思考の段階は、トップダウン的注意(意識)が働いて、何かに心が向かう志向的意識状態である。この段階で大脳新皮質が積極的に関わる。つまり、積極的志向性(注意)は大脳新皮質前頭前野が生み出す。
第三章:情報(知)の発達と階層性 10)知性、言語、思考、意識 言語 10-3-6-1)人の脳内言語構造
10-3-6-1)人の脳内言語構造
人の場合には、耳で聞いた声は、聴覚神経によって脳幹(視床)に伝わる。その後大脳新皮質側頭葉の聴覚野に伝えられる。ここで初めて音が語音(言語音)として認識される。つまり、音を言語として分類する。更に、側頭葉の別の部位で、音声語が意味と照合された上で統合されて、聞いた言葉の意味が理解できる。ここまでは受信である。発信する場合には、前頭葉で単語を組み合わせて言語による意思表示ができる。
子供の言語は、周りとのコミュニケーション(相互的意思表示)のために身につけられる。だが、次第にこの言語が自分自身の思考手段としても利用されるようになる。この心の中でのみ使われる場合には、内言という。さて鳥の場合はどの段階まで可能なのか。
10-3-6-2)三種類の言語野(言語中枢)
人にとって言語は本当に大切な機能なので、大脳新皮質に言語に関わる領域が三つもある。
(1)話し言葉(聴覚言語)の理解(意味解読)に関わるウェルニケ野(側頭連合野)
(2)書き言葉(視覚言語)の理解に関係する角回(頭頂連合野)
(3)発話(言語発信)を担うブローカ野(前頭前野)
これら三つの領域(側頭葉ウェルニケ野、頭頂葉角回、前頭葉ブローカ野)は、全て大脳新皮質に存在する。哺乳類の大脳新皮質は、哺乳類以外の鳥類や爬虫類などにはみられない。そのため、層構造をもつ大脳新皮質は哺乳類の誕生の直後に現われた進化的に新しい脳領域であることがわかる。
だがしかし、鳥類の大脳は哺乳類と並んで大きい。例えば、カラスの大脳には、霊長類と同程度の神経細胞数が含まれる。カラスが(ずる)賢いのも頷ける。
第三章:情報(知)の発達と階層性 10)知性、言語、思考、意識 言語 鳥のさえずりと言語 10-3-5-1)鳥と人の共通点
鳥のさえずりと言語
10-3-5-1)鳥と人の共通点
人と同じように、多種多様な音(声)を出すことができて、個体同士が声でコミュニケートするのは、鳥類の鳴禽類だけである。といえば、たちどころに、犬や猿も多様な鳴き声を持ち、声に感情を乗せる、と反論が来そうだ。であっても、犬や猿では、鳥のような言語(感情ではなく知性的意味を含む)に近い単語の使い分けはできない。
ということで、人と同じような言語を使用できる理由を考えてみた。まず人と鳥の共通点を挙げと、
1)人と鳥のみが完全な二足歩行をしている。鳥の前足は羽へと完全変換されているので、逆に四足歩行は不可能だが。だが、人は直立できるが、鳥の場合は、45度程度の傾斜までしか体を起こせない。
2)その結果、人も鳥も良く共鳴する長い気道が真っ直ぐに伸びている。これは、頭が立つ(上に向く)ことによって可能になる。結局は、ニ足歩行と連動する。だが、逆に、二足歩行しても言語らしき表現機能を持たない動物(例えば、カンガルー)も多い。
言語表現機能を持ち、かつ人の言葉をまねすることができるのは、鳥の内でも、インコとオウムと九官鳥だけである。
10-3-5-2)鳥の言語構造
鳴禽類が鳴く歌には、構造(外的表現)があり、しかも内容(意味)もある。例えば、アカカナリアは、鳴くのはオスだけで、鳴く目的はメスへの恋歌である。ここまでは、多くの動物にも可能である。だが、アカカナリアは、音素の組み合わせでシラブル(音節)を作り、そのシラブルを集めてフレーズ(単語)を作り、それをさまざまに並べて歌(文章)を作る。これは人の言語とほぼ同じ構造である。といっても、アカカナリアと人とでは、言語の階層の高さにかなり違いがあるけどども。
コトドリは、物真似名人で、鳥の鳴き声、人の声はもちろんのこと、車のクラクション、チェンソーの起動音、カメラの連写ドライブ音などまで真似する。
鳥がこのようなことができるのは、大脳皮質運動野が、呼吸と発声の意図的な制御が可能だからである。つまり、延髄にある発声中枢を大脳皮質運動野が直接制御することができる。この機能は、鳥と人しか持たない。
鳥の内には、単語だけではなくフレーズをも作るものまでいる。それはどういう目的があるのだろうか。多分、雄による雌への優秀さのアピールであろう。だから、構造と内容があっても、使用範囲は限られ深い意味は込められていないようだ。つまり、多様な表現力を持つが、深い内容は込められていない。人間が、言語に深い意味を乗せられる機能については、後ほど説明する。
10-3-5-3)音の左右脳への振り分け
一般には、言語音は、左脳に振り分けられ、音楽、機械音、雑音は右脳に振り分けられる。
ところで、日本人の場合には、母音、泣く笑う嘆く声、虫や動物の鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎなどの自然音、尺八や三味線などの邦楽器音は、言語と同様の左脳で聞く。しかしながら、西洋人は楽器や雑音と同じく右脳で聞く。
10-3-5-4)地と図
これは、地と図という区分けではないだろうか。地とは、背景で、図とは、前景である。私達は、あふれる程の情報に対して、地と図に、無意識的に区分けしている。図に関しては、更に分析を進めるが、地だと判定された情報は詳しく分析されずに流し去られる。
第三章:情報(知)の発達と階層性 10)知性、言語、思考、意識 言語 10-3-1)言語とは
言語
10-3-1)言語とは
言語の種類としては、聴覚的な音声、視覚的な文字、だけではなく、視覚的な身振り言語、触覚的な点字などがある。これらの感覚的なものから、具体性(聴覚性、視覚性、触覚性)を捨て去って抽象化したものが、言語一般(感覚性を伴う言語よりも更に一段上に位置する)である。
10-3-2)言語の起源
言語の起源は、例えば、幼児に見られるような、いまだ言語とはなり得ていない発声とリズム(繰り返し)を伴う、泣く笑う怒るなどの「身体表現」(脳幹発信)だろう。そしてそれらは、大脳新皮質(言語の受発信)の発達によって、いずれは「言語」に道を譲る。その前(途中)に下位階層(脳幹)の機能(言語未満の発声とリズム)は、上位階層の機能(前頭葉言語機能)が徐々に伴うようになる。かくて幼児は、泣く笑う怒る遊ぶなどの身体表現(表情と行動)と言語機能(意思表示)とが一体になって表出される。ところが、大人になると、言語機能が主導権を行使して、身体表現(脳幹主体)は寂しくも置き去りにされる。かくて大人は幼児を羨む。大人は、自分達がなくしてしまった、言語未満で表現する幼児や動物に癒し(心を緊張状態から解放し、リラックスさせる状態)を感じる。
10-3-3)意思の伝達手段
言語は、人の意思、思想、感情などの情報を表現したり伝達する手段である。心の中にあって他人から知り得ない意思、思想、感情などを、自由自在に取り出すためのタグである。または、ネットワーク(心)の海から目的のものを引き出す検索語(記号)である。SNS上で、必要なものを引き出すハッシュタグ(#)である。
注)タグ付けは任意なので、国々、民族毎に、自由に貼付けられる。
10-3-4)言葉と意味の合体
例えば、ある人が悲しみに暮れていたとする。他人は、その態度や表情から悲しんでいることは理解できる。犬もそれを理解できる。それは、態度や表情も言語と同じく意思表示だからである。これは動物にも当然存在する。
私の心の海で、今現在私の心を捉えている、あるいは覆っている事態は、他人へと直接私の心をそのまま見せることはできない。心の中で感じている主観的感情は身振りや表情や発声で大まかに見せることはできるが、詳細に渡って示すには、やはり言語を必要とする。それを間接的ではあるが、最も上手く可能にするのが言語である。
ではあるが、言語は、元々は空っぽの入れ物である。例えば、日本語を全く知らない外国人に、「悲しい」と言っても何も理解できない。外国人にとって「悲しい」と言う言葉(音声)には何も入っていないからである。そこで、泣く真似をしたり、悲しい表情を見せたりして、その言葉に情報を入れてやると、言葉の意味が理解できる。ここで始めて言葉と意味とが合体する。理解するとは、感覚したものの背後に隠れている意味を知ることである。見える構造の背後にある機能を知ることである。
10-3-5)赤ん坊と言語
新生児は、口や喉が構造的には完成しているとしても、それを操作する神経回路形成がまだ発達していない(未熟な)ので、声を発する機能が働かない。構造が完成していても神経細胞の髄鞘化が未形成である。更には、ソフトウェア(神経回路)は経験を積むことによってのみ作成され完成される。
世界には、数多くの言語が存在するが、新生児は、育つ環境に関わりなく、あらゆる音素(最小の音声単位)の識別を行う能力を遺伝的に生まれ持っている。つまり、日本人の赤ん坊をフランスで育てると、フランス語を母国語として身につける。
更に、言語に関しては、左右半球(右脳と左脳)の等価性(優位性がないこと)が5歳頃の臨界期まで続く。確率的には、言語機能は左脳が優位であるが、それが機能するのが5歳以降である、ということである。